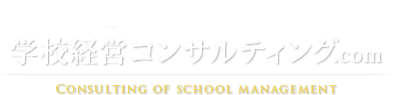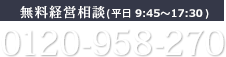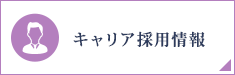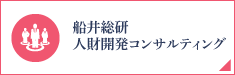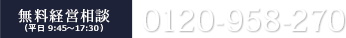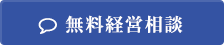【2025年最新版】専門学校の生徒募集が厳しい理由とは?18歳人口減少時代を勝ち抜く最新戦略
専門学校の経営者の皆様
「オープンキャンパスへの参加者が、年々減少している…」
「長年続けてきた広報活動の効果が、明らかに薄れてきている」
「競合校との差別化が図れず、高校生に選ばれる理由を提示できない」
このようなお悩みをよく耳にします。
現在の専門学校業界は、18歳人口の減少、大学との競合激化という、かつてないほどの厳しい状況に直面しています。
しかし、このような状況下でも、的確な戦略と実行力で着実に入学者を増やし、成長を続ける学校があるのも事実です。
このメルマガでは、専門学校の生徒募集が厳しさを増す構造的な理由を解き明かし、
この逆境を勝ち抜くための「最新戦略」を詳しく解説します。
なぜ今、専門学校の生徒募集は「待ったなし」の状況なのか
「厳しい」という言葉は聞き慣れたかもしれませんが、
その深刻度を客観的なデータで把握し、経営判断の土台とすることが全ての始まりです。
◆18歳人口の減少と大学との競合激化
専門学校の生徒募集における最大の構造的課題は、ターゲットとなる18歳人口そのものの減少です。
厚生労働省の人口動態統計によると、この減少傾向は続き、特に2031年からはさらに減少が加速すると予測されています。
これは、限られたパイを奪い合う、より熾烈な競争時代の到来を意味します。
さらに、追い打ちをかけるのが大学との競合激化です。
世間一般の大学志向の高まりを受け、大学進学率は過去最高を記録しました。
従来の専門学校進学者層が大学へ入学できるようになったことに加え、就職とのターゲットの奪い合いも激化し、専門学校市場は四方から浸食されている状況です。
◆市場縮小の影響は「不人気校」から。二極化が進む現実
市場全体が縮小する中で、その影響はすべての学校に平等に訪れるわけではありません。
地域内での立ち位置が確立できていない学校から、募集状況が大きく悪化していく「二極化」がすでに現実のものとなっています。
特に地方においては、「地域1番校」の地位を確立することが、学校が存続するための絶対条件と言っても過言ではありません。
◆経営者が今、向き合うべき「タイムリミット」
私たちがお伝えしたいのは、残された時間は決して多くないという事実です。
2031年から始まる人口の急減期に突入する前に、地域一番校としての地位を確立できるかどうか。
それが、貴校の未来を左右する重大な分岐点となります。
今こそ、経営者自身が舵を取り、未来に向けた変革を断行すべき時です。
成功校は「広報戦略」の前に「経営戦略」を描いている
生徒募集の不振を、単なる「広報の問題」と捉えていては、本質的な解決には至りません。
成功している学校は、広報という「戦術」の前に、まず自校の立ち位置を客観的に分析し、競合との差別化を明確にする「経営戦略」を描いています。
◆船井流「差別化の8要素」で自校の現在地を知る
経営戦略を考える上で有効なフレームワークが、船井流「差別化の8要素」です。
これは、学校の競争力を8つの要素に分解し、どこで競合と差をつけるべきかを可視化するものです。
戦略的(長期的)要素:立地、規模、ブランド
戦術的(中期的)要素:商品力、販促力
戦闘的(短期的)要素:接客力、価格力、固定客化力
闇雲に施策を打つのではなく、まずはこの8要素に照らし合わせて自校と競合校を分析し、
「どこを強化すれば地域1番校になれるのか」という戦いの主戦場を定めることが、全ての第一歩となります。
◆あなたの学校の「収入」と「支出」の未来予想図は?
経営者として、広報戦略と同時に考えなければならないのが、学校法人全体の収支バランスです。
学生数という「収入」を増やすことだけを考えるのではなく、
中長期的には、学費単価の向上(専科設置など)や、余剰施設を活用した新規事業による「その他収入」の確保も視野に入れるべきです。
同時に、AI活用による生産性向上などで「支出」をコントロールする視点も不可欠です。
人口減少社会を見据えた、持続可能な経営モデルの構築が求められます。
V字回復を実現した学校の共通点①:「刈り取り」から「育成」へ。早期囲い込み戦略
それでは、具体的な募集戦略に目を向けていきましょう。
近年の成功事例に共通する最大のパラダイムシフトは、アプローチする「時間軸」の変革です。
◆なぜ高3からの「刈り取り型募集」では勝てないのか?
多くの学校が高3の春から本格化させる従来の募集活動は、いわば「刈り取り型」の募集です。
しかし、このステージではすでに入学したい学校種や学科系統がある程度固まっているため、
同系統の専門学校との間で、限られたパイを奪い合う激しい消耗戦となってしまいます。
◆タイムマシン戦略:高1・2年生を未来のファンにする「育成型募集」とは
一方で成功している学校は、高1や高2の早い段階から、未来の入学者候補を「育成」するアプローチを始めています。
これは、時間を味方につける「タイムマシン戦略」とも言えるでしょう。
まだ夢や進路が明確でない段階から接点を持ち、仕事の魅力や学校の楽しさを伝えることで、競合が存在しない広大な市場で、未来のファンをじっくりと育てていくのです。
V字回復を実現した学校の共通点②:Web環境を制し、競合を突き放す
現代の高校生にとって、情報収集の主戦場はオンラインです。
このデジタル空間での存在感をいかに高めるかが、生徒募集の成否を文字通り左右します。
◆Webマーケティング1番化戦略:立地・プロモーション・訴求力の3つを制する
目指すべきは「Web環境の1番化」です。
これは、以下の3つの要素で競合を圧倒することを意味します。
Web立地1番化: SEO対策やリスティング広告により、特定のキーワードで検索された際に、常に上位に表示される状態を作り出す。
Webプロモーション1番化: SNS広告やディスプレイ広告を活用し、潜在層に広く学校の存在を認知させる。
Web訴求力1番化: 魅力的なHP・LPに加え、MEO(口コミ)対策を徹底し、信頼性を高める。
◆MEO(口コミ)対策は、なぜこれほど重要なのか?
高校生は、学校側が発信する公式情報よりも、在校生や卒業生といった第三者の「リアルな声」を信頼します。
Googleマップで学校を検索した際に表示される口コミは、彼らにとって最も信頼性の高い情報源の一つです。
MEO対策は、単なるWeb施策ではなく、学校の信頼性を構築するための最重要課題と認識すべきです。
V字回復を実現した学校の共通点③:外部を巻き込む連携戦略
自校のリソースだけでは、できることに限界があります。
成功している学校は、高校や企業といった外部のパートナーを積極的に巻き込み、自校だけでは生み出せない大きな力を創出しています。
パートナー型連携:有名企業や団体の力を借りて、自校だけでは届かない層にアプローチ
これは、地域の有力企業や団体、プロスポーツチームなどと連携し、「共同イベントの開催」や「紹介制度の運用」を行う戦略です。
パートナーが持つブランド力や顧客リスト(名簿)を活用することで、
これまで自校だけではアプローチできなかった層への認知拡大や集客が可能になります。
VIP校型連携:「附属高校」のような関係性で安定した入学者を確保
これは、特定の高校と密接に連携し、いわば「附属高校」のような強固な関係性を築く戦略です。
単発の出張授業に留まらず、
「年間を通じた教育プログラム」の共同開発や「部活動のサポート連携」などを通じて高校教育に深く入り込み、
スカウト制度や特別招待制度を活用して、安定的に入学者を確保します。
貴校の「100年学校」への道を、今ここから
本メルマガでは、専門学校経営者の皆様に向けて、
厳しい市場環境を勝ち抜くための経営戦略と、具体的な広報戦略を解説してきました。
経営戦略の重要性: 広報の前に、自校の強みを活かした「差別化戦略」を明確にする。
育成型への転換: 高3からの「刈り取り」ではなく、高1・2からの「育成」で未来のファンを作る。
Web環境の制覇: デジタル空間での「1番化」を目指し、特に口コミを重視する。
外部連携の活用: 企業や高校を巻き込み、自校だけでは生み出せない力を活用する。
経営者主導の組織改革: 全ての戦略の土台となる「実行できる組織」を創り上げる。
18歳人口の減少は、避けることのできない現実です。
しかし、これは単なる脅威ではありません。
旧来のやり方を見直し、貴校の教育力や存在価値を真に高めるための絶好の機会と捉えることもできます。
目指すべきは、地域や業界に誇る「100年学校」です。
次世代専門学校研究会:分科会
【無料・お試し参加】受付中
※申込締切:7月31日 17:00
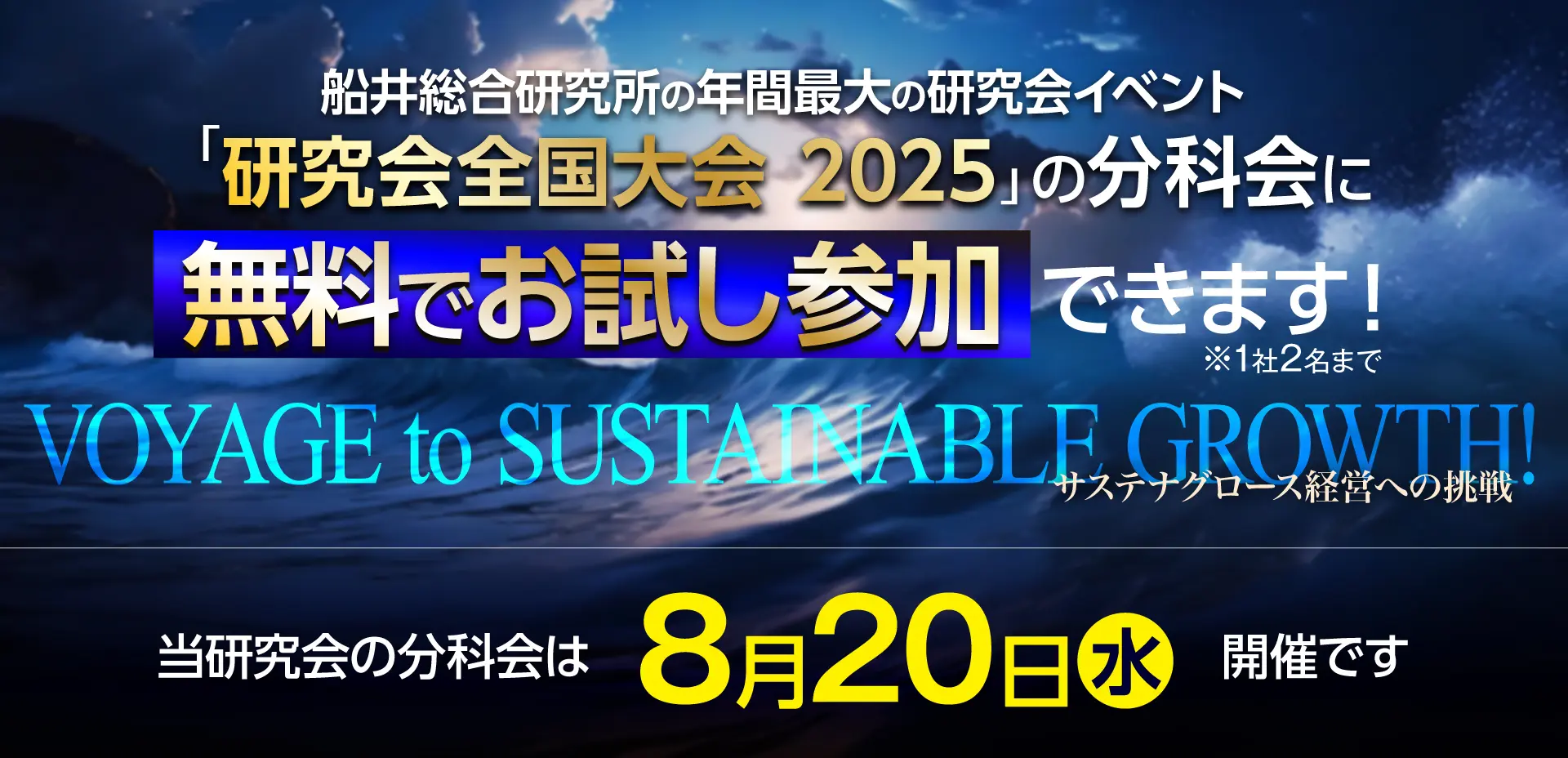
船井総研では、
会員制勉強会である
次世代専門学校研究会
を開催しております。
次回のご案内をさせていただきます。
【開催概要】
日程:2025年8月20日(水)
時間:10:00~13:00(受付 9:30開始)
場所:船井総研グループ 東京本社
サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)
アクセス:JR「東京」駅:地下直結(八重洲地下街経由)
東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
東京ミッドタウン八重洲
八重洲セントラルタワー 35 階
【講座概要】
◆ゲスト講座◆
学校法人仁多学園 島根リハビリテーション学院
教務部長:鈴木 哲 様
※この度、ゲスト様には研究会という
限られた人数での集まりということでご登壇を快諾して頂きました。
当日お話する内容は、ここでしか聞けない内容となっております。
◆船井講座◆
「地域一番校に向けた現場責任者主導の本気の改革ロードマップとは」
講師:船井総合研究所 本田耕平
◆※「サステナグローススクエア TOKYO」来場にあたり注意点※◆
・入場時に入館証(QRコード)が必要です。開催前日までにメールで届きますので、受付までにご準備ください。
・丸の内来場時より10分~15分ほど早いご来社をお勧めします。お時間に余裕をもってお越しください。
無料経営相談

無料の経営相談も受付けておりますので
お気軽にご連絡ください。