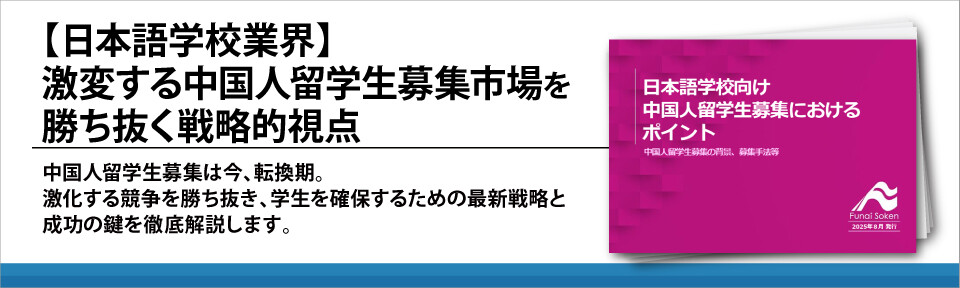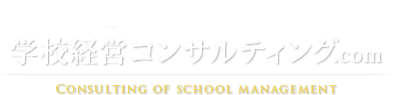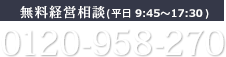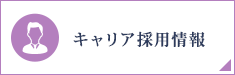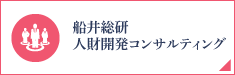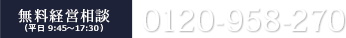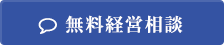【2025年最新版】日本語学校の中国人留学生募集を成功させるSNSマーケティング戦略
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の張です。
暑い日が続きますが、ご体調はいかがでしょうか?
今回は、日本語学校の経営において重要な課題の一つである中国人留学生の生徒募集について、最新の動向と具体的な募集戦略を解説します。
中国の少子化による留学適齢人口の減少や、日本語学校の増加といった逆風が強まる中、これまでの募集方法では限界を迎えます。
本コラムでは、船井総合研究所のコンサルタントが、最新の成功事例を交えながら、明日から取り組める実践的なSNS活用戦略をご紹介します。
なぜ、中国人留学生の募集は難しくなるのか?
「以前に比べて、質の良い学生の確保が難しくなった」「新しい競合校が増えて、どう差別化すればいいか分からない」
もしこのように感じている方がいらっしゃいましたら、それは日本語学校業界全体が直面している構造的な変化が原因かもしれません。これまでの日本の留学生受け入れは、中国人留学生に大きく依存してきました。しかし、中国国内の2つの大きな変化が、従来の募集手法を通用しにくくしています。
一つは、
中国の出生数減少です 。一人っ子政策の緩和で一時的に増加した出生数は、2015年から急激に減少傾向にあります。これにより、留学適齢期の人口そのものが減少し、留学生の「母数」が縮小しています。
もう一つは、
日本語学校の増加です。コロナ禍で一時的に減少した日本語教育機関・施設等の数は、2021年度以降、右肩上がりで増加しています。留学生募集市場は競争が激化しており、これまでと同じ活動を続けているだけでは、学生の確保は年々困難になります。
このように、中国の人口減少と日本語学校の増加という二重の逆風が強まる中で、競争力のある生徒募集が不可欠となっています。
「公式」から「リアル」へ:消費行動の変化とSNS活用の重要性
現代の中国人若年層は、学校側が制作した公式な広告よりも、在学生や卒業生が発信するリアルな口コミを最も信頼しています。中国の若者の消費行動は「公式広告」から「リアルな口コミ」へと変化しています。
特に、中国版Instagramとも呼ばれる「rednote(小紅書)」では、信頼できるユーザーの体験談が、学校への興味や憧れを喚起します。専門学校の入学式に参加した学生が投稿した内容に対して、留学に関する質問がコメント欄に寄せられ、投稿者がそれに回答するといった事例も見られます。
この変化に対応するためには、複数のSNS活用が不可欠です。中国の若者は、一人あたり平均6.5種類のソーシャルメディアを使い分けており、目的によって利用するプラットフォームを切り替えるのが当たり前になっています。したがって、一つのプラットフォームだけに依存したアプローチは通用しません。
留学生の意思決定プロセスは、
「認知→興味→検討→決定」の4つの段階に分けられ、それぞれの段階で、学生が求める情報と最適なSNSが異なります。
このプロセスを理解し、各SNSの特性に合わせた情報発信を行うことで、効果的な生徒募集が可能になります。
SNS活用メソッド:目的別3つの募集事例
この章では、貴校の強みや特性に応じた、3つの具体的なSNS活用戦略をご紹介します。
1. <小規模校におすすめ> 口コミ中心戦略
広告予算が少ない小規模校でも、在学生や卒業生による「リアルな声」を活用することで、信頼を獲得できます。
①在校生が、学校生活のリアルな様子をrednoteに投稿します。
②学校公式アカウントが、その投稿を再編集し、Douyinで広く拡散します。
③投稿に興味を持った入学希望者は、WeChatで個別相談や出願へと進みます。
この戦略は、広告費に頼らず、小規模校ならではの個別対応力を強みとして、信頼を築くことができます。
2. <進学実績が強い学校> 目的別プラットフォーム活用戦略
「進学に強い」「大学院進学に特化している」といった明確な強みを持つ学校向けの戦略です。
①認知:Douyinで学校の存在を発見してもらいます。
②理解:Bilibiliで授業動画を公開し、教育の質を体験してもらいます。
③信頼:Rednoteで在学生や卒業生の口コミを確認してもらい、信頼を深めます。
④決定:WeChatで個別相談に応じ、出願を促します。
学生が求める情報を最適なプラットフォームとタイミングで提供することで、興味関心をスムーズに次のステップへと繋げます。
3. <地方校におすすめ> 長期コミュニティ育成戦略
立地的なハンデを抱える地方の日本語学校でも、早期からファンを育成することで、競争力を高められます。
①早期接触:すぐに留学生を募集するのではなく、日本の文化に関心を持つ層向けのコミュニティを運営します。
②魅力発信:Vlogや写真を通じて、地方ならではの魅力(物価の安さ、豊かな自然など)を発信します。
③信頼構築:コミュニティ内で数年かけて価値提供を続け、将来の留学生にとっての「身近な相談相手」というポジションを確立します。
この戦略は、すぐに生徒募集に繋がらなくても、長期的な関係構築を通じて「第一想起」を獲得し、出願に結びつけることを目指します。
明日から取り組むべき5つの戦略的ポイント
留学生確保のためのSNS活用は、単なる情報発信ではありません。学生の消費行動の変化を理解し、彼らが求める情報とコミュニケーションを最適な形で提供する総合的なマーケティング活動です。
最後に、これまでの内容をまとめた、明日から取り組むべき5つの戦略的ポイントをご紹介します。
①一気通貫したアプローチを意識する:特定のSNSだけでなく、複数のプラットフォームを連携させ、学生の意思決定プロセス全体をサポートします。
②学生からの口コミで信頼を構築する:学校が作成する広告よりも、在学生や卒業生のリアルな声が重視されます。口コミを創出するための仕組みを構築しましょう。
③プラットフォームの特性に合わせて情報を最適化する:各SNSの文化やユーザーの期待に合わせ、ショート動画、体験談など、最適な形式で情報を発信します。
④「人」を前面に出し、親近感を醸成する:学校という組織ではなく、在学生や教職員といった「個人」の視点から情報を発信し、心理的な距離を縮めることが重要です。
⑤長期的な関係構築を目指す:WeChatなどのチャットグループを活用し、すぐに生徒募集に繋がらなくても、継続的にコミュニケーションをとり、信頼関係を深めましょう。
まとめ
中国人留学生の募集は、今後ますます難易度が高まっていきます。市場の変化を的確に捉え、貴校の強みを活かした独自の戦略を構築することが、安定的な学校経営に不可欠です。
船井総合研究所では、日本語学校をはじめとする様々な教育機関の経営課題を解決するためのコンサルティングサービスを提供しています。
「具体的な生徒募集のノウハウを知りたい」
「SNS活用をどう進めればいいか分からない」
「競合との差別化戦略を立てたい」
こうしたお悩みをお持ちの経営者様、ぜひ一度、私たちの無料経営相談をご利用ください。貴校の状況に合わせた具体的なアドバイスをさせていただきます。