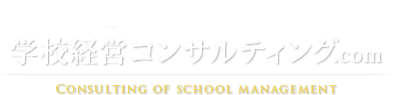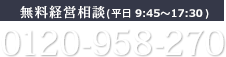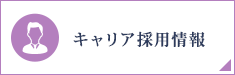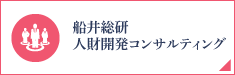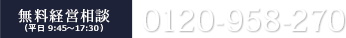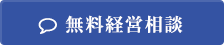大学入学改革~英語の民間試験を活用~
こんにちは。学校経営コンサルタントの林優一郎です。
本日は、平成32年度から大学入試センターに替わる新テスト「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」についてお話ししたいと思います。
文科省は8月31日、英語試験について国が認定した民間団体の試験を活用する案を公表しました。
「英検」などの試験を活用して新テストの成績として扱うとのこと。
現行のセンター試験は「読む」「聞く」の2技能について行われていますが、
ここに民間テストの「書く」「話す」を加えて4技能をテストしたいという意図です。
特にこれまで、測るのが難しかった「話す」技能については、面接や採点などに課題がありこれまで踏み切れなかったという背景もあり
民間団体へ任せる形をとるようです。
将来的には民間団体にすべての技能のテストを任せることも検討しているようです。
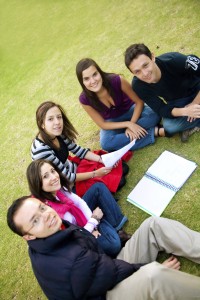
私個人としては、この変化に対しては非常にいい変化だと捉えています。
なぜか。
それはこの改革が、英語は「コミュニケーションツール」であるということを意識した改革であると感じるからです。
私は、幼少期に英語圏で生活した経験があり、今でも英語は比較的得意な部類だと思っていますが、
文法なんて知らなくても特段、問題を感じたことがありません。
ここでいう、問題というのは、コミュニケーション上のという意味ですので、
当然話している相手は違和感を持っているかもしれないですし、
一部意味が分からないと思われている部分もあったかもしれません。
しかし、それは日本語でも同じことで、言っていることがわからない人や
不思議な日本語を使う日本人はたくさんいます。
正確な文法を知らないと日本語が話せないのだとすると、多くの日本人は何も話せないかもしれません。
ただ、実際には、上記のようなことはなく、皆日本語を話しています。
これは、日本語が「コミュニケーションツール」だからです。
だからこそ、正確な文法をまず覚えてからでないと話さないのではなく、
どんどん話し、聞きながら言語を習得していきます。
英語も同じはずです。
しかし、英語の文法偏重から抜け出すのはなかなか難しいです。
やはり、現状の出口となっている大学入試改革が必須になってきます。
入口でいかに早期の教育を行っても、出口が同じなら意味はありません。
大学入試改革の動向については今後も注意深く見守っていきたいと思います。